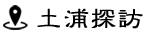-

-
土浦町道路元標
2010/11/28 文化財
道路元標とは、大正8(1919)年に国道の始まる地点を示すため、当時の道路法にもとづいて設置された標識をいう。 現在土浦町道路元標がある場所は中城通りと亀城通りとの交差点にあり、か …
-

-
聖徳太子堂
2010/11/13 文化財
聖徳太子堂は、日本文化と日本仏教の元祖である聖徳太子を祀る。 境内の聖徳太子報恩碑は、昭和11(1936)年に土浦の有志により桜川畔に建てられ、次いで昭和40(1965)年、土手の …
-

-
100本のクリスマスツリー
2012/12/14 観光
小学生や市民たちの想いが詰まった手づくりのツリーが街を彩る100本のクリスマスツリーは、1998年のTX開通に合わせてつくばセンター広場で開催された。2008年以降はつくばセンター …
-

-
中城天満宮
2010/11/27 文化財
創建は年代不詳、祭神は菅原道真で、書道、学問の信仰を集めていいる。 天神社、天神宮、天満宮などと呼ばれている。中城天満宮は、通称中城の天神さまとしてよく知られている。 源頼義・義家 …
-

-
土浦城旧前川口門
2010/11/13 文化財
この門は、親柱の背面に控柱を立て、屋根を架けた高麗門である。高麗門は城郭の門として建てられた形式のひとつで、この門も、武家屋敷であった多計郭(たけくるわ)と町屋の間を仕切る「前川口 …
-

-
南門の土塁
2010/12/18 文化財
東光寺のそば、県道24号線(土浦境線)の大町交差点に土浦城南門跡があり、水戸街道を江戸に向かうこの土浦城南門の左右、当時の上沼、下沼をつなぐ堀に沿って、土塁が構築されていた。 東光 …
-

-
サイエンス・スクエア つくば
2012/09/09 観光
産総研が行っている最先端の研究成果や社会への貢献などについての幅広い研究テーマを分かりやすく解説し、産業の基盤を支える計測標準から、ロボット、エネルギー、医療など幅広い研究テーマを …
-

-
東光寺
2010/12/18 文化財
曹洞宗。 東光寺は慶長12(1607)年、心庵春伝(しんあんしゅんでん)によって開かれたと伝えられる。 境内にある朱塗りの建物で瑠璃光殿(るりこうでん)と呼ばれる薬師堂があり、市指 …